子どもの不登校の原因は「甘え」だと言われることもありますが、はたしてほんとうにそうなのでしょうか。
結論から言うと、不登校の原因は「甘え」です。
しかし、「甘え」にも種類があることはご存知ですか。
「甘え」というと、「怠けている」「だらけている」「できるのにやらない」などと、少なくともいいイメージを持つと言う人は少ないでしょう。
不登校の原因は、この「怠けによる甘え」ではなく、別の種類の「甘え」になります。
この記事では甘えの種類や、不登校の対策方法などについて紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
怠けの「甘え」とヘルプの「甘え」
冒頭でもお話ししました通り、甘えには2種類あります。
その甘えとは、
・怠けによる「甘え」
・ヘルプの「甘え」
です。
それでは、この2つの甘えにはどのようなちがいがあり、特徴があるのでしょうか。
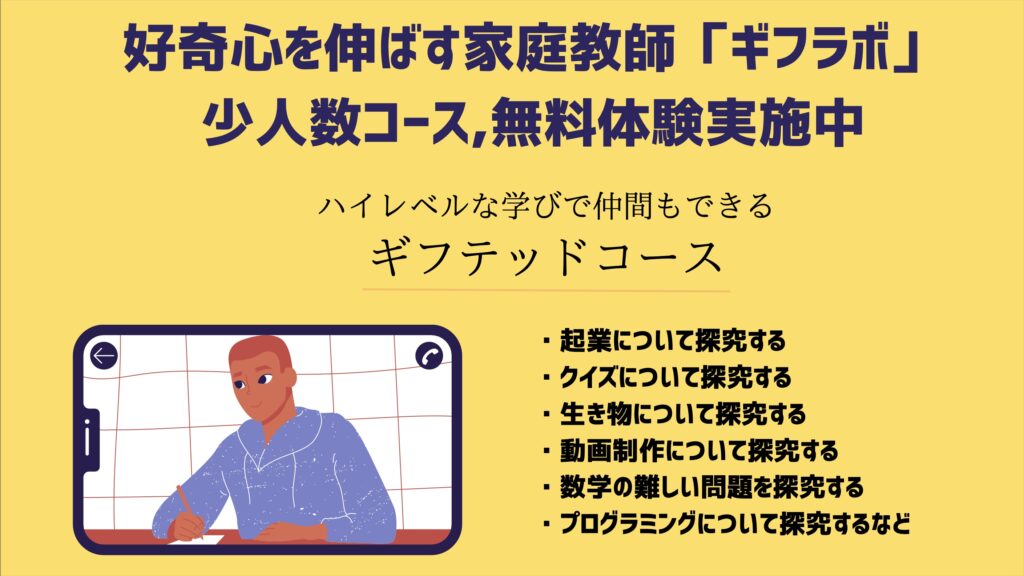
怠けによる「甘え」
怠けによる「甘え」は、「甘え」と言う言葉から連想されやすいマイナスなイメージを持つものです。
以下のような姿が、怠けによる甘えでしょう。
・だらけている
・怠けている
・できるのに、やりたくないが先行する
・気が緩んでいる
不登校の甘えは、このような怠けによる甘えではないとされています。理由としては、不登校の子どもは人一倍「学校に行かなければいけない」という思いが強い傾向にあります。
しかし、精神的なストレスや、心に負った傷により「行けなくなってしまっている」というほうがふさわしいのです。
ですので、行けるのに行けない、気が緩んでいることによりめんどくさくて行かないという心情ではないので怠けの「甘え」ではないことがわかります。
ヘルプの「甘え」
不登校の原因となっているのは、この「ヘルプの甘え」です。
ヘルプの甘えとは、「助けてほしい」「手伝ってほしい」「気づいてほしい」という子どもが親に発信する甘えです。
不登校になってしまった子どもは、学習面や人間関係などに生きづらさを感じ、殻に閉じこもってしまっています。
行かなきゃ行けないことはわかっていても、体が動かない、体調が悪くなってしまう、などと、体が学校=危険な場所として認知し、自分の身を守ろうとしている反応です。
この子どもながらのSOSの発信の仕方が「不登校になる」という形になるということです。
不登校の原因となっているのは、この「ヘルプの甘え」です。
ヘルプの甘えとは、「助けてほしい」「手伝ってほしい」「気づいてほしい」という子どもが親に発信する甘えです。
不登校になってしまった子どもは、学習面や人間関係などに生きづらさを感じ、殻に閉じこもってしまっています。
行かなきゃ行けないことはわかっていても、体が動かない、体調が悪くなってしまう、などと、体が学校=危険な場所として認知し、自分の身を守ろうとしている反応です。
この子どもながらのSOSの発信の仕方が「不登校になる」という形になるということです。
不登校の原因となっているのは、この「ヘルプの甘え」です。
ヘルプの甘えとは、「助けてほしい」「手伝ってほしい」「気づいてほしい」という子どもが親に発信する甘えです。
不登校になってしまった子どもは、学習面や人間関係などに生きづらさを感じ、殻に閉じこもってしまっています。
行かなきゃ行けないことはわかっていても、体が動かない、体調が悪くなってしまう、などと、体が学校=危険な場所として認知し、自分の身を守ろうとしている反応です。
この子どもながらのSOSの発信の仕方が「不登校になる」という形になるということです。
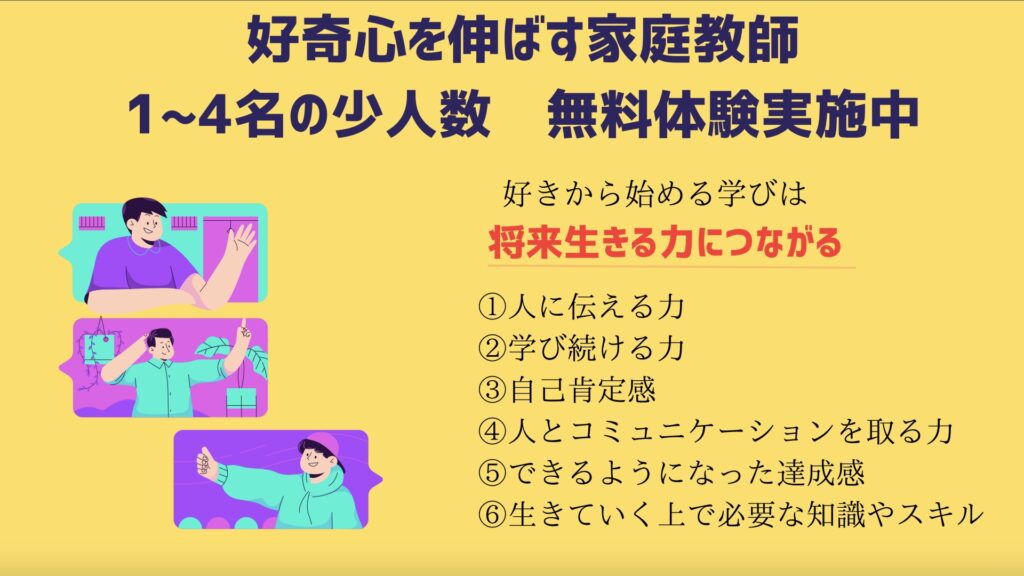
不登校の原因となるのは怠けの「甘え」への甘やかし
不登校の原因の「甘え」がわかったところで、親はどのような対応をとったらいいのでしょうか。
怠けの「甘え」を甘やかすことで起きることは
・自由=好き放題だと思い、ことの善悪がわからなくなる。
・自主的に行動することが難しくなる
・なんでも母に頼れば解決すると良くない知恵を獲得する
ということです。
怠けの「甘え」を甘やかすことが愛情ではありませんよね。自由の中にもある程度の決まりがあったり、主体的に取り組むことで得られる経験は今後の人生でとても役に立つということを考慮して対応しなければなりません。
それでは、一体どんな対応が不登校から子ども自身が抜け出すことができるのでしょうか。
不登校解消への近道となる対応を紹介します。
子どもの選択を受け止める
まず第一に行ってほしいことは、子どもへの「承認」です。不登校になる子どもは、自分の身を守るために、自分の心をこれ以上傷つけないように不登校という道を選択します。
ですので、まずは自分を大切にできたという事実を認め、受け止めてあげてください。
くれぐれも、学校に行くことを勧めたり、おだてたり、怒ることはしないようにしましょう。
親に自分の選択を受け止められた子どもは、自分が1番安心できる家という場所で心の回復のための準備を始めます。
さらには、子ども自身から不登校の原因を話してくれたり、気持ちを伝えてくれるようにもなる場合があります。
親に否定されず、しっかりと気持ちを受け止められたり、話を聞いてもらえることで、「自分は間違っていなかったんだ」「お母さん・お父さんはどんな自分でも受け止めてくれる」などという安心や自信につながり、不登校の原因の解消にちかづくことができるでしょう。
今の子どもには、「親からの承認」と「心の回復」が最も必要なのです。
愛情をたっぷり注ぐ
不登校の子どもは、何かしらのヘルプを抱えて生きています。そんな時に最も力となり必要としているのが「親からの愛情」です。
特に小学生の子どもなどは、親の影響を大きく感じる時期です。また、関係性や信頼関係も深まってくる時期ですので、余計に心身ともに不安定な不登校になっているときには親の愛情を求めています。
生きてくれていること、自分を大切に思ってくれていること、笑顔を見せてくれたことなど、ささいなことでもなんでも構いません。「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えたり、「大好き」という愛を伝えてみてください。
しかし家庭状況によっては、親が子どもに向き合いたくても就労しなければいけない状況であったり、時間を取ることができないということもあるでしょう。時間がない時や、金銭面で心配があるときには心に余裕が生まれないので、つい子どもに怒ってしまったり、焦って不登校を解決させようと促してしまうことがあります。
しかし不登校の子どもは、自分という殻に閉じこもっている状態です。この時期は周囲の反応や環境に過敏になります。親の焦りや呆れを感じ、さらに傷が深まってしまったり、反発してしまうということも考えられるでしょう。
ですのでそんなときにはスクールやカウンセラーなど、専門の機関の助けを借りるのも一つの手です。親に代わって、専任の先生やカウンセラーが子どもをサポートしてくれます。また、スクールによっては、学習をサポートしてくれたりなどのサービスがあります。
また、子どもだけではなく親のケアもしてくれ、カウンセリングをしてくれたり、子どもへの対応を提案してくれることもあります。子どもにとっても大人にとっても、専門の機関に頼ることは良い影響があるので、ぜひ自身の地域にはどんなサポート体制があるかを調べてみるのもいいでしょう。
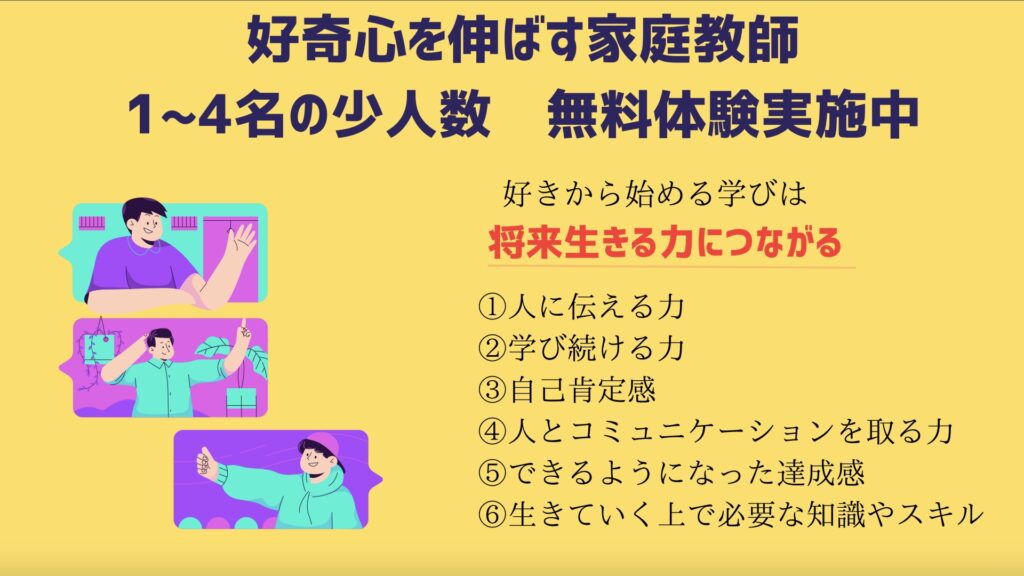
不登校解決へのステップ
実際に子どもが不登校になったさい、何から始めたらいいかと迷ったり、実際に渦中にいる場合には「いつまでこの状況が続くのか、、」と不安に思ってしまう親も多いでしょう。
不登校の子どもの気持ちには波があります。うまく進んでいたとしても、ある日突然後戻りしてしまうなどということも珍しくありません。
そんなとき、親は「うまくいっていたのに」「いつまで続くのか」という気持ちになってしまうでしょう。
不登校の子どもの状況には時期があるとされています。その時期を知ることで、いま自分の子どもがどの時期にいるのか、回復までどれくらいなのか、ということがわかります。また、「行ったり戻ったりすることがある」と初めから思っているのといないのとでは、親の気持ちの負担も異なるでしょう。
サポートをする上でも見通しがたっている方が
安心ですよね。
ここからは、それぞれの時期について紹介していきます。
前兆
不登校になる時期のことを「前兆期」といいます。前兆期の子どもの様子は以下のとおりです。
・体調不良を理由に休む日が増えた
・登校の時間が過ぎると気分が晴れ、元気に過ごす
・特定の日にち、曜日の時に欠席をする
この時から、学校を休む日がポツポツとでてきます。「学校に行きにくくなってきた」と子どもが親にヘルプを出し始める頃です。
この時、「学校に行きなさい!」「病気じゃないでしょ」「うそつかないの」などと子どもを責めるのはやめましょう。
頻繁に続くとなると、子どもからのヘルプだと思っていいでしょう。そんなときには思いを受け止め、自宅で回復できるようにさせてあげてください。
深い傷を負っておらず、もやもやしている子どもの場合は、この時期にしっかりと回復できたり、親に受け止められて自分に自信がつくことにより登校し始めることができる場合もあります。
進行、継続
前兆があり、そのまま進行・継続してしまう状況です。このような時期の子どもに見られるのはこのような様子です。
・友達と距離を置き始める
・学校の話になると怒る、場所を離れる
・落ち込んである
・夜遅く起きていて、昼まで寝ている
この時期の子どもは、「学校に行くなければいけないのにいけない」ということに対して不安や葛藤、焦りが混同しているとても不安定な状況にあります。
自己肯定感が下がりがちで、自分のことを責めてしまう傾向にあるため、親は自己肯定感が上がるような声掛け、前向きに過ごせる会話を心がけましょう。
何か家のことをやってくれた時に感謝をしたり、笑顔でいてくれたり、話してくれたという些細なことでもいいので「嬉しかった」などと気持ちを伝えてみてもいいですね。
混乱
不登校の気持ちの波があり、今後の不安や今の心の傷や嫌な思い出がフラッシュバックしてしまうことがあります。
・攻撃的になる
・大きな声を出す、暴れる
・学校のことを話し始める
このままでいいのかな、という不安がぐるぐると頭を回り、不安や焦りでいっぱいいっぱいになっているのが言動に現れるようになります。
しかし一方で、「もうこのままでいい」などと、学校の優先順位が下がってくる時でもあります。
自分には学校は必要のない場所という考えに至ることが多いです。
ですので、この時期に学校であったことをすんなり話し始めることがあります。そんなときには想いに共感しながら話を聞いたり、話してくれたことに感謝をしながら、学校を前向きに捉えられるように言葉掛けをしてあげられるといいでしょう。
ここまでしっかりと向き合い、愛情が伝わっている場合には、「そっか、そうだよね」「家族がいるから自分は大丈夫かもしれない」「頑張ってみようかな」などの勇気が生まれたり、1歩踏み出そうとすることもあるでしょう。
回復、復活
前兆、進行、混乱の時期を経て、自分に自信を持つことができたり、気持ちが満たされることで学校に登校できるようになります。
はじめは登校し始めても次の日は休むなど、休む日もありますが、それも少しずつ少なくなっていきます。
ここで注意が必要なのは、登校できるようになったからといって完全に回復したと思わないことです。学校という場所は、不登校の子どもに対して万全を期しているものの、やはり友達関係などまでは管理ができません。ですので、友達からの心無い言動で、再度不登校になってしまうという恐れがあります。
ですので、親に求められる対応は、自己肯定感を高められるよう、学校に行こうと思ったこと自体を認めて褒めたり、「無理しなくていいよ」「自分のペースでいいよ」と子どものペースで回復できるよう促してあげることです。
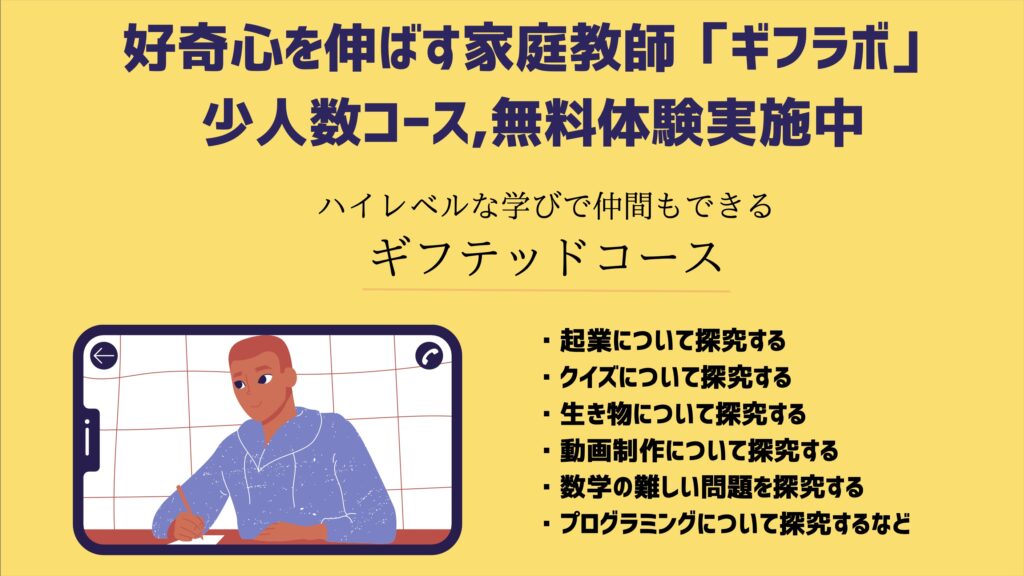









コメント