現在、日本の中で不登校の生徒がどれくらいいるかご存知でしょうか。
文部科学省が算出している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、不登校の割合は年々増えています。2022年の結果では、全国小中学校の不登校児童生徒数は過去最高の24万4940人で、前年度からは24%増加した数字になっています。
また、昨年比と比べ最も多く増えているのが小学生の不登校で、不登校率が一番高いのは中学生です。不登校の増加は深刻な問題として各メディアでも取り上げられています。
もしかすると、この記事を読んでいる貴方は、子供が不登校で頭を悩ませているかもしれません。自分の子供だけが学校に行けていないのだと焦っているかもしれません。しかし、今の時代に不登校になってしまうことは珍しくありません。
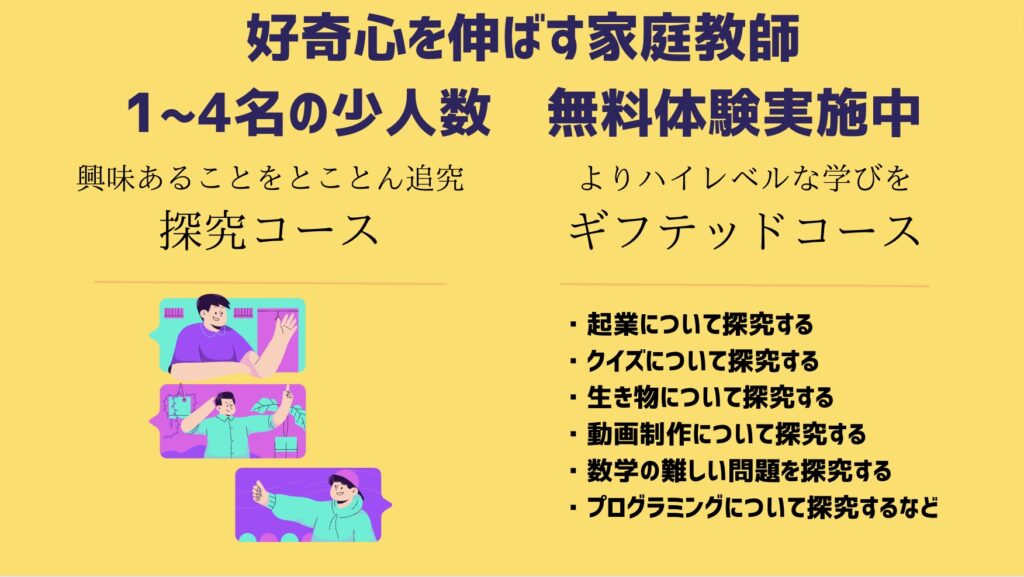
不登校の原因
では、毎年何故これだけの人数が不登校になってしまっているのでしょうか。
不登校になってしまった原因は何なのでしょうか。
不登校と聞くと、いじめや暴力が頭をよぎる方も少なくないかもしれません。しかし、不登校の主な原因はいじめではありません。寧ろ、いじめは割合的には極僅かです。
文部科学省の調査では、実際に「不登校になったきっかけ」についてアンケートをとっています。
不登校を克服、あるいは予防するためには「学校に行きたくない理由・きっかけ」を知ることが大事です。まずは、不登校になる原因を見ていきましょう。大きく分けると4つの区分に分けられます。
①学校に関係する状況 15%
②家庭に関係する状況 20%
③本人に関係する状況 60%
④その他 5%
原因として6割を占めるのは「本人に関係する状況」です。
それぞれ順番に具体例を挙げて見ていきましょう。
①学校に関係する状況 15%
原因が学校にあるものです。
・いじめ
・いじめを除く友人関係のわだかまり
・教師との問題
・学業不振
・入学や転入、進級の不適合 など
いじめを含む友達関係や教師との関係、勉強の遅れなどがここに該当します。
ニュースや新聞などで大々的に報道されやすいのがいじめに関わる問題であり、いじめが不登校の原因であると目にしたり耳にしたりすることが多いですが、いじめが不登校の直接の原因だと断定されている割合は、全体の0.3%に留まっています。
尚、「学校に関係する状況」の中で1番多いのは、「いじめを除く友人関係のわだかまり」2番目に多いのが「入学や転入、進級の不適合」となっています。
②家庭に関係する状況 20%
原因が家庭にあるものです。
・家庭の生活環境の急激な変化
・親子の関わり方や家庭内不和
・親との別離不安
・家庭の経済状況 など
離婚やリストラなどによって生活が困窮した、今まで通りの生活ができなくなった、といった家庭環境の変化も不登校に影響します。
また、家庭環境が変わったことで日頃の疲れや夫婦喧嘩によるストレスが溜まり、子供に八つ当たりをしてしまうと家庭内で子供の居場所がなくなってしまいます。すると子供は非行に走りやすくなります。逆もまた然り、子供が親に依存しすぎている場合も別離不安となり不登校になりやすいです。
③本人に関係する状況 60%
原因が本人にあるものです。
・生活リズムの乱れ
・遊びや非行
・無気力、不安 など
不登校の理由の中で、一番多いのが実は「無気力、不安」です。この項目だけで全体の49%を占めています。つまり不登校のうち、10人に4~5人の割合です。この統計が不登校は甘えと言われる理由の一つにもなっています。
意外に感じるかもしれませんが、もし貴方の子供が学校に行きたくないと訴えていたとして、その理由が無気力や不安である可能性は十分にあります。
④その他 5%
・病気、体質、障害
・その他
見落とされがちですが、子供の発達障害や体質が不登校の原因になっている場合もあります。
「知能的には問題がなくても、読み書きが苦手」だったり、「理解力が高いのにじっとしていられない」といった状況があれば、それにあった適切な教育サポートをする必要があります。
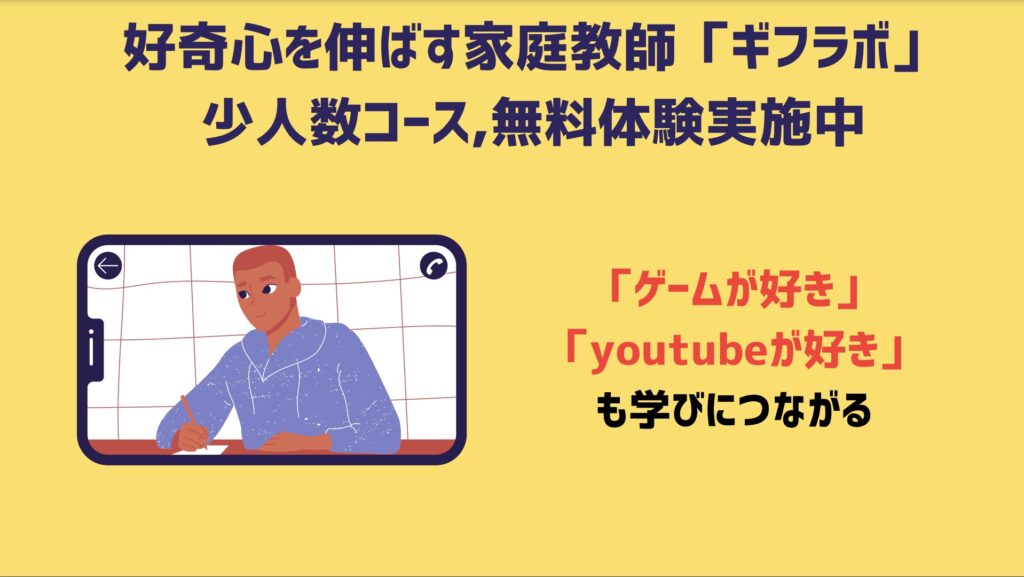
不登校の子供に対する、親の5個のNG行動
では、不登校の原因が分かったところで、「引き籠りになってしまった子供へはどう接すれば良いのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
実は、親が子供のためを思ってやっていた事が、逆に子供の状況を悪化させているかもしれません。状況を改善しようと考えたことが、逆に不登校を長期化させてしまっているかもしれません。
ここでは、「学校に行きたがらない子供」へ、絶対にしてはならない5つのNG行動を解説します。
誤ってやってしまっていないか確認してみましょう。
1.叱る、問いただす
子供が不登校やひきこもりになった場合、「いったいなぜ自分の子どもが?」という不安から、本人を叱ってしまったり、原因を問いただすことがあると思います。しかし、これは逆効果です。
学校に行きたがらない子どもに対して、決して責めてはいけません。
学校に行けない状況を強く責められると自己肯定感が低くなり余計に学校に行けなくなるからです。
子供が学校へ行かなくなってしまった不安や焦りから、怒る・叱る・躾ける・問いただすなど、子供を責める行動に出てしまう方も少なくありませんが、子供の気持ちに寄り添った対応をすることが重要です。
また、不登校やひきこもりの「回復」に関する研究の論文では、子供と学校側の認識の相違について指摘しています。子供本人が思っている事と、学校側が把握している事が異なっている、ということです。原因を本人に問いただすことは、教師や周囲の人間との認識の違いから余計に本人を混乱させる可能性もあります。
2.本気で聞かない、聞き流す
自分が仕事や家事介護などで忙しい時、「学校に行きたくない」「今日は休みたい」と言われたらつい聞き流してしまうかもしれません。朝の忙しい時間などは特に「後にして」「わがまま言わないで」と一蹴してしまったり、ずる休みだと思って本気にしないこともあると思います。
しかし、「休みたい」の言葉が子供が勇気を振り絞って訴えたSOSだとしたらどうでしょうか。本気にせず聞き流すと小さなサインを見逃してしまいます。小さなサインを見逃してしまうと、気付いた時には状態は更に悪くなり、回復が難しくなっているかもしれません。
子供の声にはきちんと耳を傾け、はぐらかしたり聞き流したりしないことが大切です。その上で、子供の声に対し親の意見もしっかり伝え対話をすると親子の信頼関係は高まり、状態は好転しやすくなるでしょう。
3.感情的になる
不登校や引き籠りから回復する過程で、家族が信頼関係を適切に築くのはとても重要なことです。
しかし自分の子供が不登校になると、親は子供に対して叱咤激励を行いがちです。自分は良かれと思ってやっていることかもしれませんが、結果的に子供を精神的に追い詰めてしまっていることが多いです。
激しい感情で接することは子供の不信感を強める原因となります。
そして親の心に余裕がない状態では子供も安心することは出来ません。
心配や不安、焦りというのは中々自分でコントロールできない気持ちではありますが、なるべく落ち着いて冷静な対応を心がけましょう。
4.親や保護者だけで解決しようとする
子供が学校へ行かなくなってしまった時、中々周りに相談できず保護者のみで解決しようとする傾向があります。しかし、自分の力だけで何とかしようとするのはよくありません。
客観的にアドバイスをくれる人や専門知識を持っている人がいないと、無意識のうちに子供を傷つけてしまう可能性があります。子供の不登校を直そうとして気付かぬうちに自分の考えを押し付けてしまったり、子供を否定してしまっているかもしれません。
自分の子供だから、と責任感を持つのではなく、子供のために周りの意見を取り入れるようにしましょう。
5.学校を休ませないようにする、再登校に拘る
不登校の子供がいる親は、子供を無理にでも登校させるべきか頭を悩ませているかもしれません。不登校や引き籠りが長期化すると子供の将来が不安になりますよね。
しかし、無理に登校させてしまうと事態を悪化させることになります。
強制することで子供は反発し、回復までの時間が長くなってしまうからです。
不登校やひきこもりの解決方法を研究した論文「『不登校』の問題とその解決」では、「不登校やひきこもりの初期は休ませることが基本であり、学校以外に居場所を作ったのち、保健室登校などの段階を踏んで徐々に登校していくことが有効である」とされています。
不登校には必ず原因があるはずです。
まずは一度ゆっくり休む時間を設け、学校へ行きたくない原因を見つけましょう。
不登校の子供に対して、親がするべき4つの対応
先程のNG例とは反対に、親が子供にしてあげられることがあります。それぞれ見ていきましょう。
1.子供の話を聞き、打ち明けた時は感謝を伝える
子供は不登校になるほど大きなストレスや悩みを抱えています。
子供が話したくない様子であれば1日に少し話すだけでも十分です。真摯に向き合おうとする姿を見せれば、頑なな心も徐々に溶けて悩み事を話してくれるでしょう。
悩み事を打ち明けてくれた時は、「よく言ってくれたね」「話してくれてありがとう」と感謝を伝えてください。感謝を伝えることで子供の心は軽くなり精神状態が緩和されるため、回復も早くなります。
2.休んでいいと言葉で伝える
不登校になってしまうと「早く回復しなさい」「保健室でもいいから行きなさい」と強く言ってしまう親もいるかもしれません。しかし、まずは、子供の苦しい気持ちを受け入れて認めてあげることが大切です。
学校に行きたがらないというのは、学校、勉強、人間関係などに向かうエネルギーが無い状態です。そのためNG行動例でも記載した通り、無理に登校させるのは逆効果です。
事態を悪化させないためにも、家庭の居心地を良くして「今は休んでもいいんだよ」と伝えてあげてください。
3.親子の信頼関係を築き、家庭を安心できる環境にする
子供にとって家庭を安心できる場所にしましょう。
子供の気持ちを受け入れたり、意見を尊重するコミュニケーションや会話を心がけてください。否定せずに認めてあげる、受け止めてあげることが大事です。
子供は「親は自分を受け入れている」と思うことで、登校再開も含めて次の一歩に進むための気力が回復していきます。家や家族が安心できる場所であることで、子供は家庭を足がかりに外の世界にも踏み出せるのです。
尚、子供が「親と話したくない」のであれば、ひとまずは無理に会話をする必要はありません。無理に話を聞き出すことは警戒心や無気力を高めてしまうので、子供が話せる状態になるのを待つことも重要です。
4.サポート団体を利用する
自分の子供が不登校だったり、学校に行きたくないと言い出した場合、「自分の子の問題だから」と周りの手を借りず自分で何とかしようと考えるかもしれません。しかしNG行動に「親や保護者だけで解決しようとする」とあるように、子供を追い詰めてしまうかもしれません。
サポート団体の利用は非常に有効的な対応策です。話をするだけで親子の不安やストレスの緩和に繋がります。
また、様々なケースを通じて蓄積した専門知識やノウハウに基づいて適格で具体的な解決策が得られることもあります。子供のサポートだけでなく、「不登校の子を持つ親」のサポートも一緒に行ってくれるため、親子の強い味方です。
不登校やひきこもりは社会問題となっており、行政・民間を問わず様々な機関が支援活動を行っています。
例えば公的機関では、以下のような施設が不登校やひきこもりのサポートを行っていますので、相談してみると良いでしょう。
・教育支援センター
・精神保健福祉センター
・ひきこもり地域支援センター
・地域若者サポートステーション など
親自身が落ち着いて冷静に考え、子供に意見の尊重を
子供が学校を休みがちになってしまったら、親が不安や焦りでいっぱいになるかもしれません。
ストレスがたまってしまったり、何とかしなくてはと1人で空回りしてしまうことも珍しくありません。
しかし、子供を思っての言動が逆効果を生んでしまっている可能性もあります。
まずは、親自身が落ち着いて、状況を冷静に考えてみてください。
子供が何故「学校に行きたくないのか」しっかりと意見を聞いてあげ、子供の話を頭ごなしに否定するのではなく、きちんと話し合いをしてみましょう。今すぐに解決させてすぐに登校させようと焦るのではなく、長い目で子供のことを考えて対応することがとても大切です。
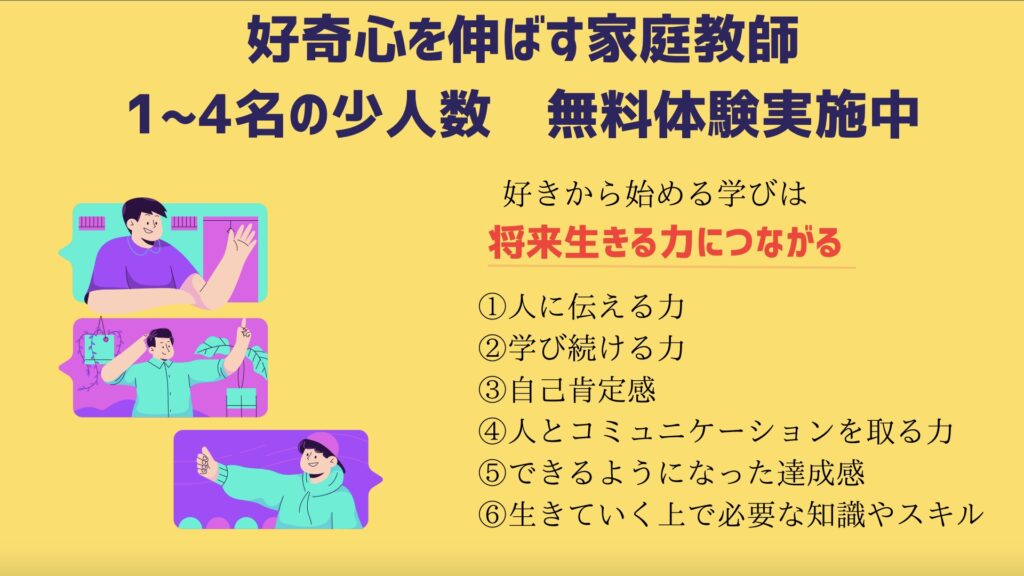









コメント