お子さんは朝ちゃんと起きて学校に行けていますか?何度も遅刻してしまう、朝起きるのが辛い、夜なかなか寝付けないなどの症状がある場合は「起立性調節障害」の可能性があります。
起立性調節障害は身体の成長期に自律神経の発達が付いていくことができずバランスが乱れ、睡眠障害や低血圧などの様々な症状が出現してしまう病気です。
この記事では起立性調節障害について、その主な治療法2つを説明させていただきます。
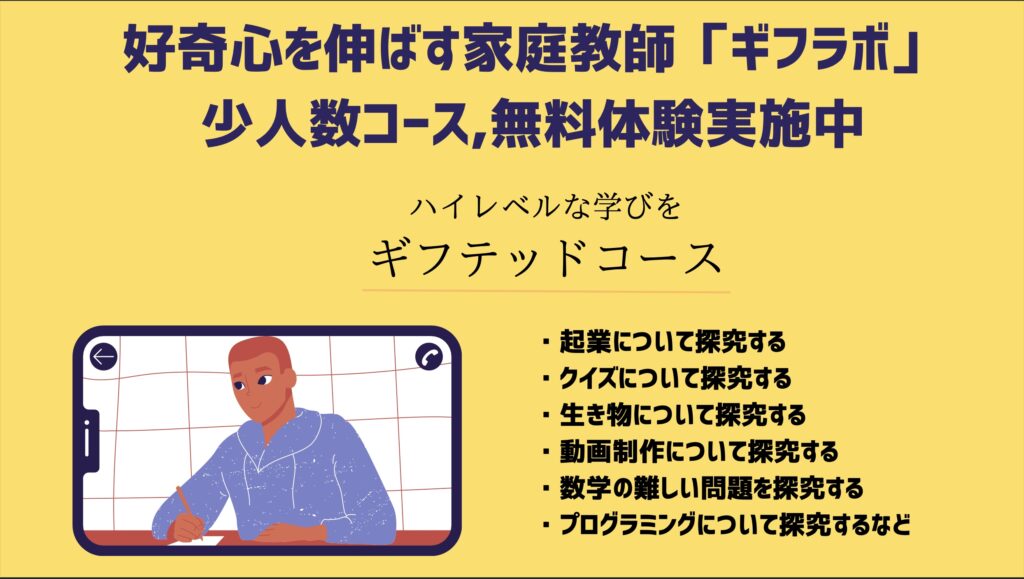
子供を不登校にする起立性調節障害とは
まず、起立性調節障害は思春期小児に多く見られる自律神経の機能失調です。主な症状として
・立ちくらみ、めまい
・入浴時、または嫌なことを見たり、聞いたりすると気分が悪くなる
・少し動くと動機または息切れを起こす
・朝なかなか起きられず、午前中調子が悪い
・顔色が悪い
・食欲不振
・疲れやすい
・頻繁な頭痛
・乗り物に酔いやすい
などがあります。これらの症状の3つ以上当てはまった場合は起立性調節障害の可能性が高いです。
このような症状であるため病気だと気づかれないことがほとんどです。また起立性調節障害には血圧や脈拍の変化によって以下の6つのサブタイプがあります。
どのタイプか判断するのかは新起立試験という検査を受けます。起立性調節障害と診断した後に10分間安静の状態で横になった後立ち、心拍数や血圧の変化を測定するというものです。
1.起立直後性低血圧
軽傷であれば徐々に一般的な血圧に戻っていき、症状も緩和されるが、重症の場合には、回復が遅く頻繁に失神する可能性がある。
2.体位性頻脈症候群
起立に伴う血圧低下はないが心拍数の著しい上昇がある。その結果めまいや倦怠感、頭痛などの症状が現れる。また本人は動機を自覚していない場合が多い。
3.血管迷走神経性失神
起立中に突然血圧が低下する。脳の血流不足になり、意識が薄れたり急に意識がなくなったりする。また、血管迷走神経性失神は先の起立直後低血圧や体位性頻脈症候群の併発するケースがあり、重症型に分類されることが多い
4.遷延性起立性低血圧
起立直後は問題ないが、立ち続けていると血圧が低下し始めるのが特徴。
5. 脳血流低下型
起立後の血圧や脈拍には何の問題もないが脳血流だけが低下していく状態
6.過剰反応型
起立直後に血圧が以上なほど高く、めまいなどの症状を引き起こす
以上のように起立性調節障害といっても様々なタイプが存在し、体に起こる反応もそれぞれ違ったものになってきます。そのため専門の病院でしっかりと診断してもらい、適切な治療をしてもらうことが重要になってきます。
起立性調節障害を発症しやすい人の特徴
ここでは起立性調節障害を発症しやすい人の特徴について紹介します。
起立性調節障害の約半数は遺伝によるものだと考えられています。 約半数とは驚きですよね。
それだけ、遺伝による原因が大きく中には、「うまれつきで起立性調節障害になる可能性もある」と言われています。
また、起立性調節障害を発症する男女比は男1女1.5~2と女性のほうが発症する可能性が高いことも特徴です。
そのほかに
・朝起きるのが苦手
・頻繁に立ち眩みをする
・小食
・水分・塩分をあまりとらない
・気を遣いすぎる
・常に精神的ストレスがある
などの人は自立神経が乱れ、発症しやすい傾向があります。
起立性調節障害の治療期間は
軽症 : 2~3か月
中等症: 1年
重症 : 2~3年
となっています。この中でも全体の約8割が重傷で社会復帰までに2~3年かかります。このように起立性調節障害はすぐに治る病気ではなく、時間をかけてゆっくりと治していくものなので「学校にずっと行ってない、どうしよう、、」「これ以上症状が悪化したら、、」などは考えずに気長に治療していくことが大切です。
起立性調節障害はその症状の特徴から「怠けているだけ」「ただの甘え」と理解されないことが多いです。なので学校や親などの周りの大人が理解を深め、子供をサポートしていくことが必要です。
例として特別教室や家庭教師・オンライン学習などの学習環境を整えてあげたり、カウンセリング・家での気遣いなど学校や外に行かなくても子供の将来・精神のケアのために行動することが必要になります。
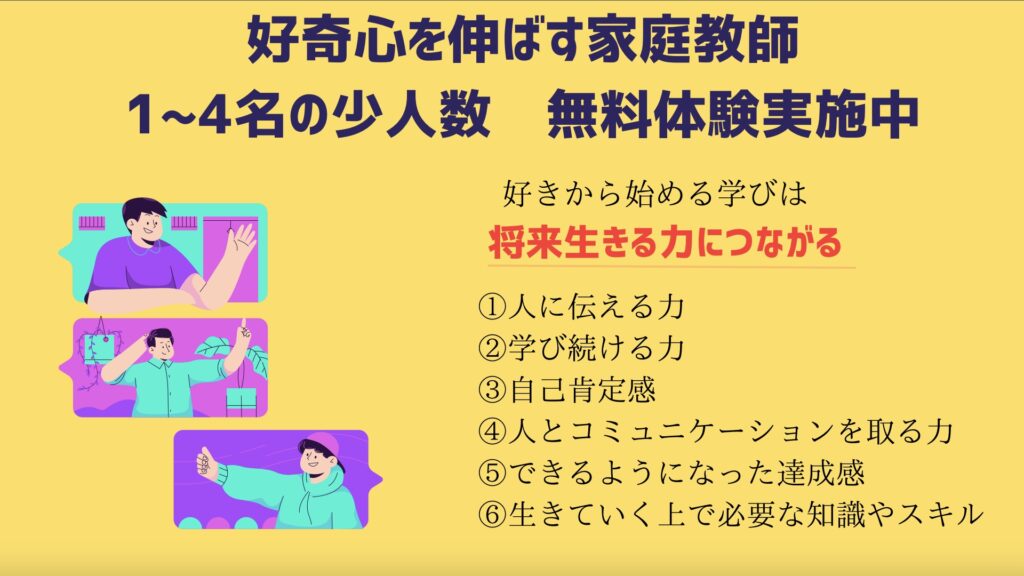
起立性調節障害の治療法
これまで起立性調節障害の症状や特徴を説明してきましたが、それではこの病気はどうやって治療していくのでしょう?治療法には主に2つの種類があります。
1.薬物治療
まずは薬物療法です。ですが薬物療法は次に説明する「非薬物療法」を行ったうえでの治療法になります。中には市販されているものもありますが、薬物療法だけでは効果が少ないと言われているので、その点に注意しながら読んでいただきたいです。
起立性調節障害の治療に用いられる主な薬と副作用については以下の通りです。
塩酸ミドドリン(メトリジン、メトリジンD錠など)
効果
血管を収縮させ血圧を上げる働きがあり、起立性低血圧に広く使われ、起立直後性低血圧や体位性頻脈症候群などでは最初に使われます。効果はゆるやかに現れるため、しばらくは様子を見ます。
副作用
頭痛、動機など
プロプラノロール(インデラルなど)
効果
心拍数を減らし血管を収縮させる働きがあり、高血圧や不整脈のための薬です。体位性頻脈症候群に使われます。
副作用
だるさ、めまい、除脈、低血圧、手足の冷え、稀にぜんそく発作や心不全
メシル酸ジヒドロエルゴタミン(ジヒデルゴットなど)
効果
血管を収縮させ、起立時に血液が下半身に貯留するのを防いで症状を和らげます。起立直後性低血圧の人が、塩酸ミドドリンで効果がない場合に使います。
副作用
吐き気、嘔吐、食欲不振など
メチル硫酸アメジニウム(リズミックなど)
効果
交感神経の機能を促進させて、血圧を上げる。起立直後性低血圧の人が、塩酸ミドドリンで効果がない場合に使用する。
副作用
動悸や頭痛、ほてりなど
また、起立性調節障害の薬は効果を感じるまでに約1~2週間かかります。起床時間の30分から1時間までに服用しなければいけないので、子供にとってはかなり面倒だと思うかもしれません。
症状の改善を目指すならやはり毎日欠かさず、長期的な服用が非常に重要になってくるので親も気にかけるようにしましょう。
もし副作用などで服用を中止したい場合は必ず医師に相談してください。突然やめると症状が悪化する可能性があります。
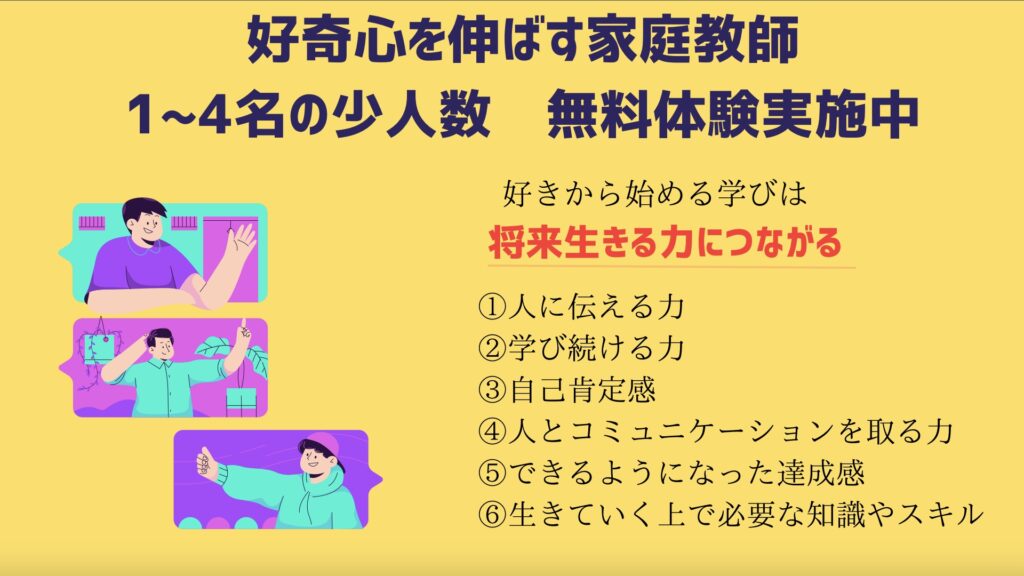
2.非薬物治療
次に非薬物療法についてです。薬物療法の副作用のようなデメリットもなく、簡単にできるものが多いのが特徴です。
動きはゆっくり・長時間同じ姿勢は避ける
朝起きて立ち上がる時はいきなり立つのではなく、30秒ほどかけてゆっくりと動きましょう。また同じ姿勢をずっとしてると血流が低下してしまう恐れがあるので、足を交差させたり、足踏みなどをして常に血流が良い状態を保ちましょう。
太陽の光を浴びる
起立性調節障害は自立神経のバランスが乱れることにより、体内時計がずれ、朝起きれなくなったり、夜なかなか寝付けなくなります。
そこで太陽の光を浴びることで脳に光刺激を届け、体内時計のずれを修正することができます。
また、朝起きれず日光を浴びれないという方は朝日と同程度の光を出すことができる「光目覚まし時計」というものもあります。
水分をとる
体内の水分が不足すると、血液量が減ります。すると低血圧になりやすくなってしまいます。そうならないためにもこまめな水分補給をします。目安としては一日1.5~2ℓとりましょう。
また、ジュースではなくなるべく水を飲みましょう。ジュースを飲みすぎると糖尿病や肥満につながってしまうためです。
塩分を摂取する
塩分の多い食事をとると、体内の浸透圧によって血液中の水分量が増え、血管の壁にかかる抵抗が上がり、血圧が上がります。
そのため塩分の多い食事をとり、血液量を増やすことで症状を緩和・改善することができます。目安は一日10~12gです。
散歩など軽い運動をする
下半身の筋肉量が減ってしまうと、血流が悪くなり低血圧が悪化してしまう可能性があります。かといって下半身の筋肉量を上げようと激しい運動をすると心拍数が上がり動機や息切れが悪化してしまいます。
そこで適度に始めやすく、下半身の筋肉量を増やせる運動として散歩が効果的です。
また一定のリズムを保ちながら歩くことで自律神経を整えることも期待できます。
サプリメント
先に説明しましたが、起立性調節障害の薬物治療に使用する薬には副作用があります。
お子さんが起立性調節障害で副作用がある薬を飲ませるのは抵抗がある方もいらっしゃると思います。
そのような場合にはサプリメントという手段もあります。サプリメントはあくまで健康食品で薬よりは効果は望めません。ですが朝起きられるようになる可能性があるサプリメントもあります。
手が入りやすく、中断もしやすいのでサプリメントを摂取することも視野に入れてはどうでしょうか。
整体
整体に通ってから「症状が軽くなった」という親御さんの経験談はネットに多くあります。これは起立性調節障害が体の不調からくるものだからと考えます。
例えば姿勢が悪く、呼吸がしづらい、内臓が疲労している、脈拍が早いなどがあります。こういった不調を治していけば起立性調節障害を治療することにつながっていきます。
整体では自律神経を整え、自分で血圧をあげられる体を作ることができるのです。
また、起立性調節障害のための整体法や整体だけではなく、生活相談をしてくれるところもあるようなのでどういった対応をすればいいのか、どんなことに気を付けるべきなのか等も聞きたい方は一度探してみてはいかがでしょうか。
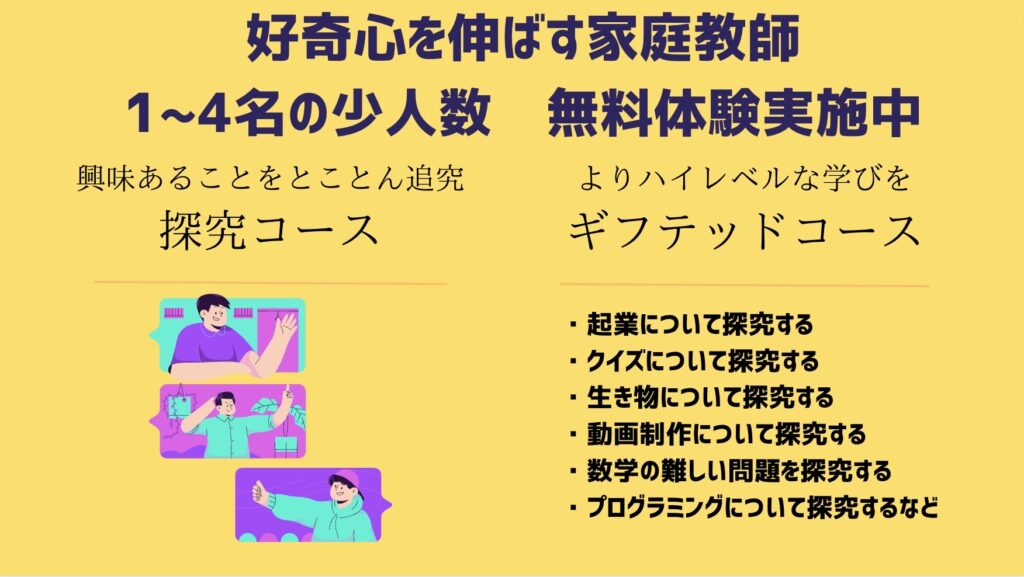









コメント