子供が不登校なのは親のせいではない
皆さんは、日本にどれくらいの不登校児童生徒が存在するか知っていますか?
2022年10月27日、文部科学省から「問題行動・不登校調査」の結果が発表されました。
その結果によると、全国小中学校の不登校児童生徒数は過去最高の24万4940人、前年度からは24%増加し、深刻な問題として各メディアでも取り上げられています。
更に、小学校と中学校の長期欠席者も含めると、その数41万人にのぼります。この数字は、クラスに1人以上不登校生徒がいるという計算になります。
学校へ行きたくないと思い、登校することに抵抗を示す子供は年々増えています。そして、子供が不登校になるとよく言われるのが親の陰口です。
「親が悪い」「親の育て方に問題がある」「親が甘やかしているからだ」などと言われます。直接指摘されることはないかもしれませんが、近所や学校で噂になったり、言葉ではなくても視線を向けられることもあります。
そうすると、親は自分を責めてしまうかもしれません。自分が惨めに思えたり、落ち込んでしまうかもしれません。しかし、不登校は誰にでも起こり得ることです。
不登校は親のせいではありません。親は悪くありません。
貴方がもし、自分を責めているのであれば、自責の念にかられる必要はないのです。
不登校心理カウンセラーの前田氏は「不登校は決して両親のせいではない、それは断言できます」と話をされています。
しかしそうは言っても、自分のことを責めて、疲れてしまったという方もいるのではないでしょうか。そういった方は以下のような方法でリフレッシュしてみるのはいかがでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。
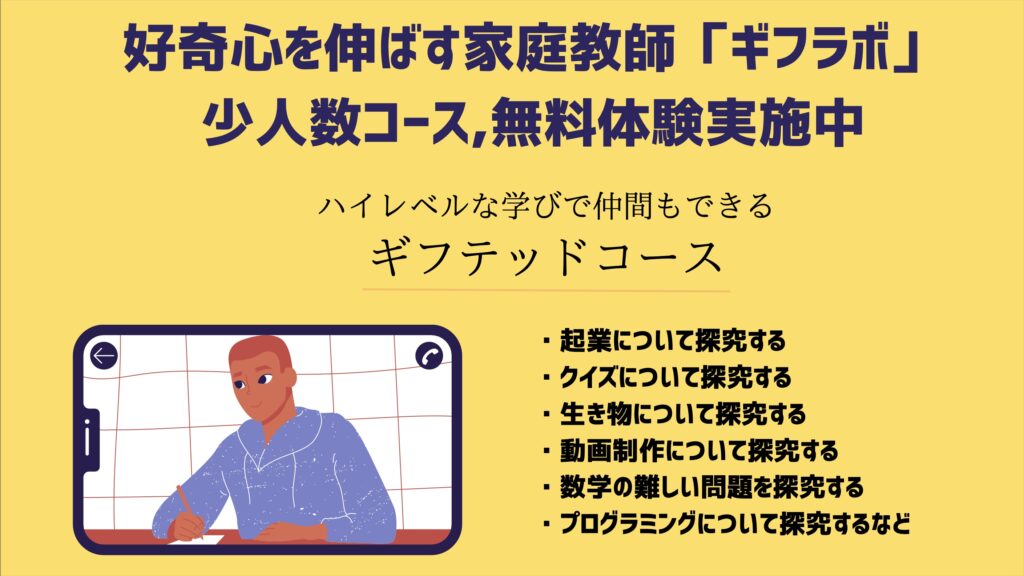
外に働きに出る
子供が不登校だと、親は心配のあまり日常生活に支障をきたすことがあります。「子供の傍にいてあげたい、しかし生活があるから簡単に仕事も辞められない」と、特に母親は仕事を辞める方がいいのか続けるべきか、悩んでしまうかもしれません。
結論からお伝えすると、どちらが最適かは家庭環境や不登校理由によって異なります。
不登校という根底の問題に対して、母親が家にいることによって問題解決に向かう場合と、逆に不登校が長期化してしまう場合があるからです。
では、どのようにして働き方を考えれば良いのでしょうか。
まずは、「働くか働かないか」について判断方法の例を紹介します。
1.子供に聞いてみる
外に働きに出るべきか、出ないべきかを、子供に聞いてみるのも一つの手です。聞く時は、なるべく柔らかい言葉を使いましょう。「貴方のせいで仕事をするかどうか悩んでいる」ではなく、「会社を辞めて家にいようと思うのだけど、どう思う?」などと質問してみると良いです。
家に居てほしいという回答があった場合は、親が家にいることによって不登校が解決に向かう可能性が高いです。
逆に、「1人で大丈夫」と答える子もいます。親に迷惑をかけまいと遠慮していることもありますが、親が会社を辞めて家にいることを望まないケースも多いです。
家にいてほしくないのに親が家にいる、という状態になると子供は学校でも家でも居場所を失い、部屋に引き籠るという悪循環に繋がることもあります。
2.経済状況を考慮する
仕事を続けるか否かについて、どうしても考えなくてはならないのはお金の面です。経済的に不安定になることは避けましょう。
川崎医療福祉大学の研究では、「経済的に不安定になることによって家庭にも様々な影響が発生し、親子関係や家庭の状況を悪化させることにも繋がる。貧困と不登校には関連性がある」という事を指摘しています。
生活維持が難しくなってしまうと家庭環境の根本が崩れてしまいます。これでは子供のケアは出来ませんので、しっかり金銭面も考慮する必要があります。
3.自分自身にストレスが溜まりにくい環境を選択する
親が仕事を辞めた方が良いかどうかは、子供の問題だけでなく親自身の問題でもあります。今まで会社の中で働いてきた環境が一変し、家の中で子供と二人きりになり、悩みを抱える我が子とじっくり向き合うことになります。
この環境の変化がストレスになり、親自身に疲労感が溜まっていきます。疲れからイライラして子供を叱る、短気になるなど、かえって状況を悪化させてしまう場合もあります。
仕事を辞めるか否かは、親自身が自分のストレスをどこまでコントロールできるか、自身の精神が健康な状態をどこまで保てるか、にもよります。子供の心だけではなく、自分のメンタルと向き合うことも大事です。
では、実際に「仕事は辞めず、外に出て働く」という答えを選ぶ親はどれくらいいるのでしょうか。
2022年4月にクラウドワークスで実施されたアンケートでは「子供が不登校だった時に自分は仕事をしていたか?」という質問に対し、76%が「仕事をしていた」と答えています。
そのうち、外に出ず在宅ワークをしていたのは17%でした。
上記の数値を見ると、過半数以上の親は「外に出て働いている」ということになります。
外に出て働いた親からは、実際に下記のような声がアンケートに寄せられていました。
・自分の時間と家族の時間の切替が上手くできた。
・同僚に話したら相談にのってもらえた。
・収入が増えたので子供を塾に通わせることが出来た。
・仕事中は家庭のことを忘れられるので気分がすっきりする。
上記のように外に働きにでることで得られるメリットもあります。
勿論、不登校の子供を持つ親全員が働いた方が良いと言い切れるわけではありません。しかし、「子供の事や家庭問題だけに頭を使い、心が疲弊していく」という状態に陥らないよう、自分にも配慮した選択をすることが大切です。
趣味や気分転換をする
外働きをすることで思考や気分をすっきりさせることが出来たと述べている親もいますが、実際に「気分転換」をすることはとても重要なことです。
子供は、よく親を見ているものです。親の様子がおかしかったり、毎日疲れ気味だったりすると、子供は不安な気持ちになります。また、ずっと誰かと一緒にいて1人になる時間がない状況は、子供にとっても親にとっても負担になることがあります。
自分のこと、子供のこと、どちらを考えるにしても、心の負担を軽い状態に保っておきましょう。適度な息抜きをしないと息が詰まってしまいます。
ここでは、おすすめの気分転換方法をご紹介します。
1.早朝の外食
早朝は人が少なく、空気も澄んでいます。
ファミリーレストランや喫茶店、カフェなどに1人で入り、お気に入りのメニューや一服できるドリンクを頼むのは気分転換にはうってつけです。
また、合わせて好きな音楽を聞いたり、早朝の読書もおすすめです。
頭がクリアになっている時間帯でもあるので、心身共にリフレッシュできるでしょう。
2.早朝の散歩
早朝は人通りが少なく、自分の時間に浸かることができます
好きなことだけ考えて散歩するのが良いです。
身体を少しでも動かすことは脳に刺激を与えることにもなります。
自分の思考が冷静になり物事を前向きに捉えることができるようになります。
3.ストレッチ
ゆっくり呼吸をしながらのストレッチは心身をリラックスさせる効果があります。
また、思い立った時に気軽にできる気分転換方法です。
不登校という問題に直面していると、心や身体に負担が溜まりやすく肩こりがおこりやすくなると言われています。肩こりの原因はストレスです。
呼吸を整えながらストレッチを行い、健康を意識してみましょう。
4.楽しむことを罪と思わない
真面目で一生懸命な親であれば「子供が不登校なのに自分だけ楽しむなんて出来ない」と考えることがあるでしょう。しかし、親が笑えていないのに、不登校で落ち込んでいる子供が笑えるようになるでしょうか。
子供はよく親を見ています。親自身が想像するよりもずっと多く、子供は親を観察し、気持ちを察しています。だからこそ、子供より先に親が笑っていることが重要です。
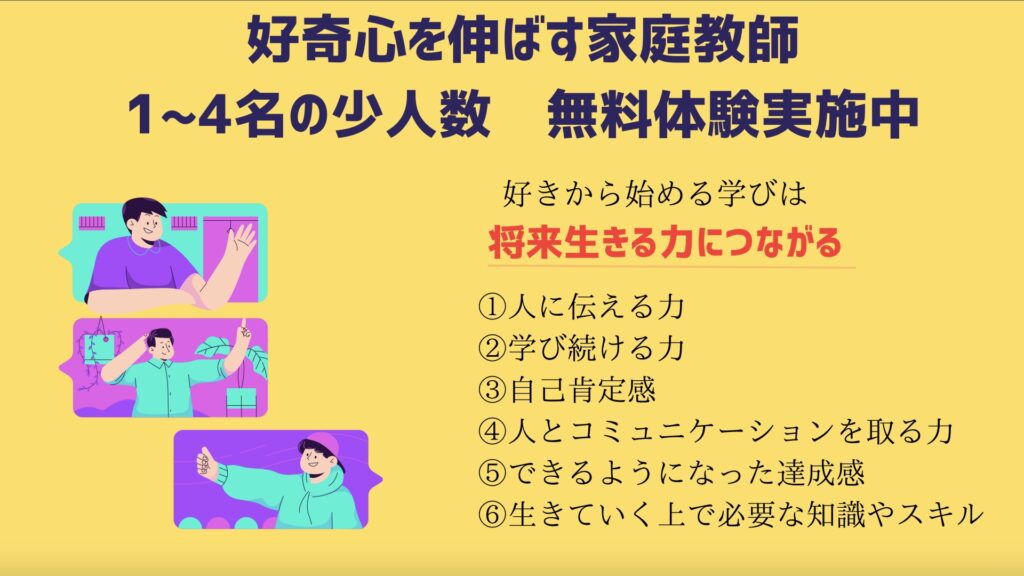
子供にも1人の時間や気分転換の時間を確保する
親だけでなく子供にも心身共にリフレッシュできる環境を与えてあげるのが大切です。そこで、おすすめはやはり散歩です。実は、気分をリフレッシュさせるということだけではなく、「不登校の子供には散歩が効果的」な理由があります。
理由1.ひきこもりを防ぐ
理由2.運動不足を解消させる
理由3.セロトニンを分泌させ、精神的ストレスが軽減される
理由4.視覚や聴覚から得る情報が感動や発見につながり行動量が上がりやすい
人を行動させるには、心情の変化や感動が必要です。
そのため、上記の理由を話したり文面で見せたりしても、「すぐに散歩しよう」とはなりません。理屈ではなく、最初は親が子供を連れ、体験させてあげることが必要です。
例えば最初は、散歩をしながら気になったお店に入ったり、昔行ったことがある飲食店に入ったりしながらお気に入りの場所を見つけましょう。
道の途中の景色や空、植物の写真を撮ると、良い意味で心が刺激されたり、それをSNSやブログに投稿してみると周りとの繋がりを感じられるかもしれません。
散歩途中に親から子に何か面白いエピソードを聞かせてあげても良いですし、兄弟がいれば兄弟同士の秘密の会話も何かのきっかけになるかもしれません。
実際に行動してみて心が動けば、あとは1人でも外に出かけるようになります。
〜すべきという固定概念を捨てる
子供の様子を見ていて、どんどん不登校の状態が酷くなっていくと不安になるものです。生活時間が崩れたり、時間や曜日の感覚がなくなるのではないか、更にはこの先社会で生きていけるのかと漠然とした悩みもあるかもしれません。
しかし、心配に思うあまり何度も指摘してしまうと親子関係が拗れることもあります。
あなたがもし不登校で、毎日のように親から
「勉強しなさい」
「なんで学校にいかないの」
と言われていたらどうでしょうか?
おそらく「自分のことをなんで理解してくれないんだ」と思って、ますます殻に閉じこもるでしょう。
そのため子供と接する際に「〜すべき」という固定概念を一度捨てる必要があります。
子供が不登校となった時、以下の点を意識して接してみましょう。
・学校に行かないと社会で通用しないという固定観念を捨てる
・必ず学校に行かなくてはいけないという固定概念を捨てる
・不登校の原因特定により、不登校を受け入れることも考える
・通信制、定時制、技能連携校などを考える
子供の不登校に対して、大人は不信感を強く抱きます。また、日本では周りの目を気にしてしまう傾向も高く、周りと違っていると悪目立ちすることもあります。
その結果「学校に行って周りの子と同じように生活するべき」「不登校は甘えだから厳しくするべき」「先生の話に従うべき」などと縛られた概念で物事を考えてしまいます。
こうであえるべき、という考えを一度取っ払い、柔軟に考えてみましょう。固定概念を捨てることで事態が回復したり、好転することは珍しくありません。また、考え方を固定しないというのは親が子供にしてあげられることでもあります。
子どもの良い面を見る
不登校になってしまった子について、親はもしかしたら子供をついつい責めてしまいたくなるかもしれません。子供を追い詰める言葉を使わない方が良いことは分かっているけれど、叱ったり責めたりする言葉が止められない、という状況は少なくありません。
これは、親のフィルターが関係しています。
フィルターとは親自身が育ってきた中で摺り込まれた思い込みや信念です。このフィルターが働いたまま子供を叱ってしまうと「私は正しい、貴方は間違っている」というメッセージになり、子供は心を閉ざしてしまいます。
そこで、子供を否定するのではなく、良い面を意識するようにしましょう。
「少しやっただけでも、まずは行動してみたことを褒める」「昨日と少しでも変化があれば、よく頑張ったと伝える」「間違っていても自分で考えた行動であれば、決断したことを認める」などです。子供にも効果があり、また親自身もネガティブな感情をポジティブな気持ちに変換しやすくなります。
実際、これらを意識することで無口だった引き籠りの不登校生徒が毎日笑顔で過ごすまでに回復した事例もあります。
また、夜遊びや非行を行うような不登校生の場合、「人を傷つけない、法に触れない」は前提ですが、帰宅したら「まずは帰宅したことを褒めてあげる」ことが重要だと心理学教員も説いています。
子供の良い面を見つけ、サポートする上では、親は子供に振り回されるのではなく不動の心を持ち、大きくどっしりと構えている必要があります。
そのためにも、本記事で記載した通り、親は自責の念にかられるのではなく、気分転換をして、固定概念に捕らわれず子供に接しましょう。
そんな親の対応は子供もしっかり感じ取り、事態は良くなっていくはずです。
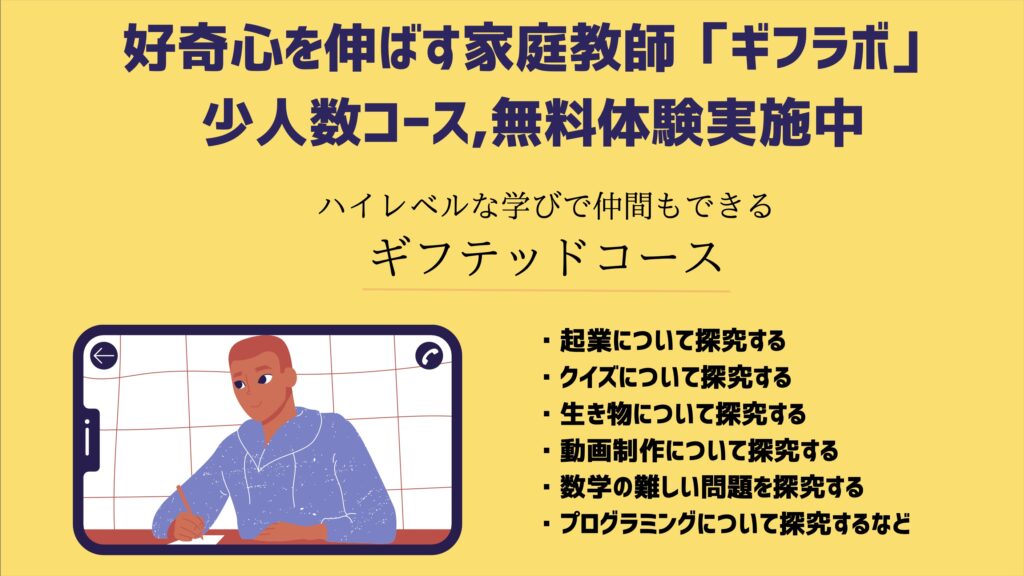









コメント