ギフテッドとは
ギフテッドという言葉をご存知でしょうか。
海外では広く知られている言葉です。日本ではまだ認知が高い言葉ではないかもしれませんが、近年では、テレビや映画などでギフテッドが取り上げられることもあり、「ギフテッド」という言葉を聞いたことがなかった方々にも知られるようになりました。日本では北野武さんがギフテッドとして知られています。
ギフテッドは英語のgiftedの単語に由来しています。日本語でギフトというと、贈り物という意味がありますが、それに似ており「神から授かった特別な贈り物(=才能)」という意味です。鬼才、天賦の才などの言葉がぴったりでしょう。
ギフテッドは、生まれつきの特性であり、特定の学問や芸術性、創造性、言語能力などにおいて、先天的に高い知性や共感的理解、倫理観などを持っている人のことを指します。そして、ギフテッドの基準として、IQ130以上が目安とされています。
日本でもIQ130以上の人は約250万人といわれています。意外とみなさんの身近なところに、ギフテッドはいるのかもしれません。
それでは詳しく見ていきましょう。
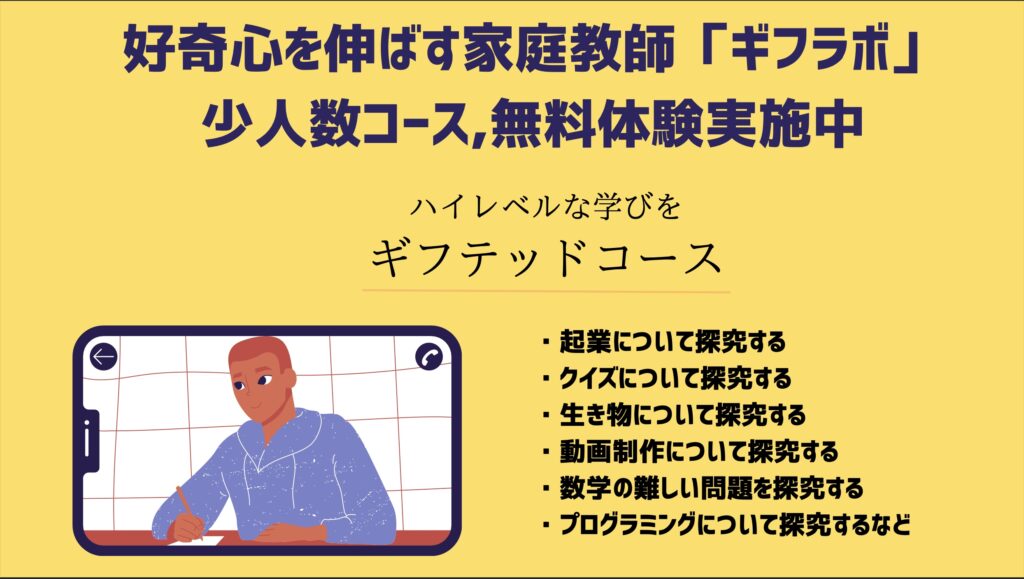
ギフテッドの子の能力について
ギフテッドは生まれつきの特質と考えられています。つまり教育熱心な親によって、年少より特別な早期教育や英才教育を施したり、親や本人の努力で優れた成績を収める優秀な子供とは違い、潜在的に備わっている高い能力です。
ギフテッドの定義は、文献や著書によって様々な表現の仕方がありますが、アメリカ連邦政府の定義では「知性、創造性、芸術性、リーダーシップ、または特定の学問分野で高い達成能力を持つため、その能力をフルに開発させるために通常の学校教育以上のサービスや活動を必要とする子供」としています。
では、「高い達成能力を持つ」とは、具体的にどういった状態なのでしょうか。
ワシントン州立大学人間発達学専任教員のポーター倫子氏は、優秀な子供とギフテッドを比較し次のような8つの事例を挙げています。
優秀な子供
①一生懸命努力する
②学校が好き
③友達といることを好む
④良い考えを持っている
⑤単純で順序立てたやり方を好む
⑥自己の学習成果に満足する
⑦課題を6-8回で習得する
⑧グループの中でトップの成績を収める
ギフテッド
①遊び半分でやってもテストの成績が良い
②学ぶことが好き
③大人といることを好む
④常識外れた考えを持つ
⑤複雑さを求める
⑥自己を厳しく非難する
⑦課題を1-2回で習得する
⑧グループの枠を超越し、基準に当てはまらない
必ずしも全てがこの特徴に当てはまるとは限りませんが、上記を見比べると「自分の中で一生懸命努力し、与えられた結果を期待通りにこなし、学校で友達と過ごすことが好き」な傾向が優秀な子供にはあります。
それに対し、ギフテッドは「僅かの努力で与えられた課題を軽々こなし、優れた知性や感性で常識を突破し、より多くを大人と過ごす」傾向があることが分かります。
また、上記で挙げた特徴以外に、ギフテッドは常に多様な知的刺激を望み、興味がある分野を自分の好む学習方法で極めて深く掘り下げて探求する傾向があります。そのため、結果的に学んだ分野が高いレベルに到達することが多いです。
高いレベルに到達する例として次の項目が挙げられます。
・小学生の時に、量子力学や相対性理論を理解した。
・譜面が読めないが音階を感覚で理解し、楽器を弾けた。
・日本の中学生の年齢で海外の大学に合格し、入学した。
尚、興味関心のあることには凄まじい力を発揮しますが、「強い感情や意見を持っているが、答えを知っていると退屈に感じてぼんやりしてしまう」という特徴もあるようです。
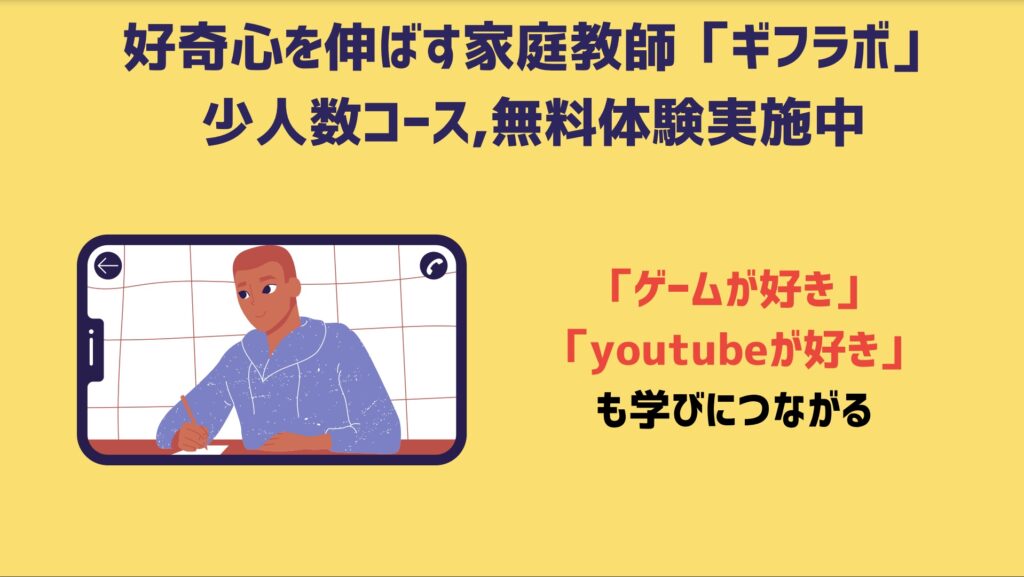
ギフテッドと発達障害の違い
ギフテッドと発達障害という言葉を比べると、「ギフテッドは突出した才能を持ち、成長や発達スピードが早い」「発達障害は普通の子供に比べ発達が遅く、行動面や情緒面において不安定」というように真逆に捉える方もいるかもしれません。
しかし、ギフテッドという言葉を調べると、発達障害を事例に出し比較や説明しているものをよく目にします。
では、どうしてギフテッドと一緒に発達障害が挙げられるのでしょうか。
まずは発達障害の定義を見てみましょう。
発達障害とは
発達障害とは、生まれつきの脳機能の働き方によるもので、同じ障害名でも特性の表れ方が違います。身体や、学習、言語、行動の何れかにおいて不全を抱えた状態で、他人との関係づくりやコミュニケーションなどが苦手とされています。
例えば、多動性障害(ADHD)や学習障害、自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群、自閉症など)が含まれます。
この発達障害の特徴がギフテッドの特徴と重なって見えることがあり、誤診されるケースが少なくありません。
海外では、誤診から必要のない薬を服用し、精神的に不安定になったというケースもあります。ポーター倫子氏は、ギフテッドである可能性を考慮して対処する必要性があると説いています。
誤診されやすいケース①多動性障害(ADHD)
例えば、知的好奇心の強いギフテッドの子供は、通常の学習環境では満足できません。知りたい・調べたい・考えたい衝動から、先生や両親を質問攻めにする、興奮してじっと座っていられないというような行動をとることがあります。
これが、多動性障害(ADHD)の特徴と一致しています。
誤診されやすいケース②アスペルガー症候群
例えば、ギフテッドは特定の分野に強い関心や拘りを持ち、周りが見えなくなるほど熱中して孤立してしまい、同年代の子供達と馴染めないことがあります。
これが、アスペルガー症候群の特徴と一致しています。
2E(twice-exceptional)という概念
中には、ギフテッドと発達障害の両方を持つ子供もいます。IQも非常に高く、通常の子供とは違う個性を持っている一方で、社会性が低い、文字が書けない、動きや衝動を止めることができないという特性を持ちます。
こういった子供たちは「二重に特別」という意味で「2E(twice-exceptional)」と呼ばれています。
では、ギフテッドと発達障害はどのように見分けたら良いでしょうか。
それぞれポイントを紹介します。
①ADHDとギフテッドの違い
どちらも幅広い興味や探求心を持っているという点に類似があります。
しかし、ADHDの場合は「興味の移り変わりが激しく一貫性がない」、ギフテッドの場合は、「全てに繋がりを求める」という違いが見られます。
もし、興味を持つ事柄に一貫性や類似性、統一性が見られるのであれば、それはADHDではなくギフテッドかもしれません。
②アスペルガー症候群とギフテッドの違い
どちらも集中する力が高く継続力があるという点に類似があります。
しかし、アスペルガー症候群の場合は「拘りがあり、ひとつの事柄に対し過集中になる」、ギフテッドの場合は「繋がりのある幅広い分野に没頭した結果、それが拘りになる」という違いが見られます。
どうして集中しているのかを注意深く見て、一時の拘りではなく一つのことを広い視野で掘り下げているのであれば、ギフテッドかもしれません。
ギフテッドの子の能力を伸ばすには
『ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法』の著者、北海道教育大学旭川校教授・片桐正敏氏は「ギフテッドという言葉を耳にすることは増えたが才能ばかりに注目され、問題が置き去りになっている」と述べています。
この問題とは、高い知能機能を持つ故に困っていることが周囲に伝わりづらく、誰にも助けを求められないまま悩んでいるというものです。そのため、生きづらさを抱えていることが多いとも言われています。
ある分野に対して理解が遅い子供と同じように、理解が早い子供にもケアが必要です。
具体的に見ていきましょう。
①我が子がギフテッドだった場合、親が子供にしてあげられること
ギフテッドの子供は、一見遊んでいるように見えても、実は色々と想像しながら思考を組み立て鍛えていることが良くあります。また、「褒められたい、満点を取りたい」という理由ではなく「面白いからやっている」という知的好奇心を満たすことが基盤にあります。
そのため、親は「そのやり方は普通ではない」「学校ではそうは習わない」と押さえつけるのではなく、「見てあげる、聞いてあげる、共感してあげる」ことが大事です。その過程で、子供が何を強みに持っているのか、才能を知ることも意識しましょう。
ギフテッドにとって、良い影響を与えるイベントや刺激的な場所があります。才能を知るきっかけにもなりますので、下記に一例をご紹介します。
・芸術的な場所(美術館、博物館、科学館等)
・コンクールや大会(音楽、絵画、頭脳を競うもの等)
・キャンプやコミュニティ(大人も集まる場所)
②学校教育に求められること
ギフテッド教育が盛んなアメリカでは、例えば「ギフテッド向けのクラスを設置する」「飛び級を認める」「ギフテッド向けの集中講義を行う」など、成長速度に合わせた教育がされています。ギフテッドが持つ才能、所謂「強み」は配慮、支援すべきであるという考え方が重要だとされているからです。
日本では全員が同じスピードで学ぶことを重要視していることが多いです。そのため、突出した才能を持つ子供の扱いに困ってしまう先生も多く、ギフテッドの子供に疎外感を与え、結果的に馴染めない環境を作る原因にもなっています。
しかし、最近では日本でもギフテッドに特化したクラスを設けているところもあります。
才能あるギフテッドの芽を摘まないために、日本でもギフテッド教育を拡張していくことが求められるでしょう。
上記に挙げた2点の共通点は、ギフテッドの能力を伸ばすには周りの協力が必要不可欠であるということです。
周りと合わせることで抑制させるのではなく、やりたいことにどんどんチャレンジすることができる環境を周りがサポートしてあげることが、ギフテッドの能力を伸ばすには重要です。
③プロの力を利用する
ギフテッドの子の居場所を提供している「ギフラボ」なら、お子さんに合った講師が、興味のあることや、勉強の伴走をしてくれます。
興味があれば無料体験へ申し込んではいかがでしょうか?
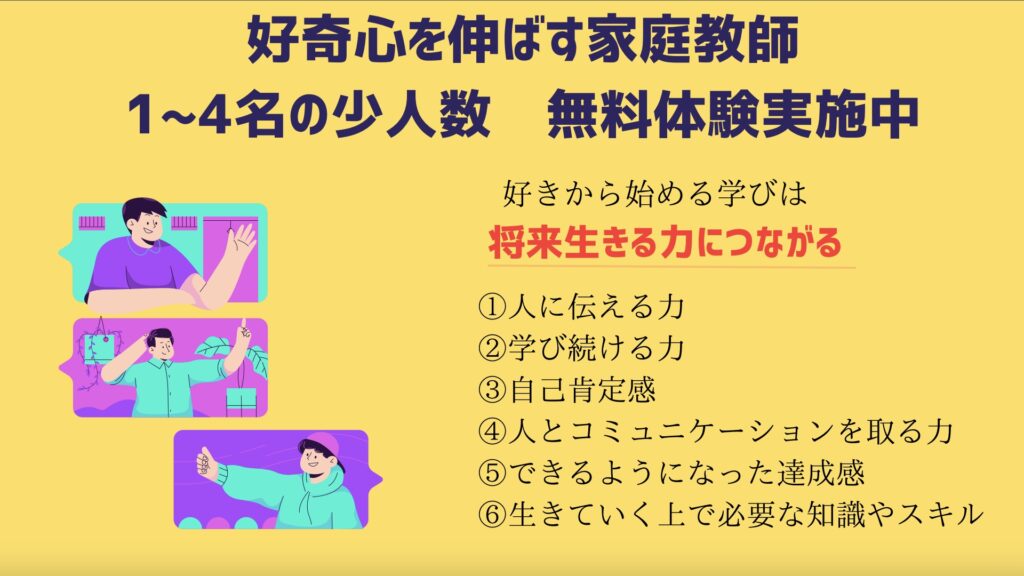









コメント